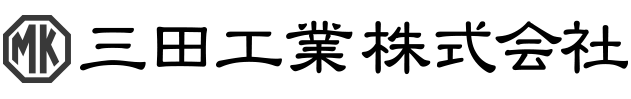さまざまな方法がある曲げ加工の種類をわかりやすく解説

形状や断面に合わせて
金物の曲げ加工はさまざまです。種類や用途に合わせて適したものを選ぶようにしましょう。
・型曲げ
・フランジ成形
・送り曲げ
が大きく分けた曲げ加工の種類です。
型に固定し圧を加える方法、複雑に曲げた製品を作り出す方法、型に固定せずにラインの中で送りながら曲げ加工をする方法になっています。
今回は、金物の曲げ加工について、種類や方法をわかりやすく解説します。
原理
板は中心を90度方向に押すと、外側が伸び、内側が縮みます。つまり、内側に縮みが起きたときに反りが起きる原理を利用して、曲げ加工を可能にするというわけです。
この原理によって起きる力は曲げモーメントと呼ばれています。曲げモーメントの力は、かかる圧力と距離をかけたもので、距離と曲げモーメントは比例します。
距離が大きいときには、幅の狭い製品だと折れたV溝部分に落ち、反対に小さいと反りが生じます。
仕上がりに不具合が起きない距離は、板厚の8倍で、加える圧についてもこれを基準に算出されることがほとんどです。
材料
曲げ加工は、ステンレス鋼などと、非鉄金属材料であるアルミニウムなどに使われる材料に分けられます。
それぞれの解説
では、ここからは
・型曲げ
・フランジ成形
・送り曲げ
について、詳しく解説します。
固定し圧を加える方法
金物を型に固定し、圧を加えて曲げを起こす方法が型曲げです。
型曲げは、ワークを固定して上から圧を加えるものや、側面からワークを曲げる方法などがあります。これらは、突き上げや迎え曲げと呼ばれます。
型曲げの方法が適している金物は、板または棒状でワークを単純な断面の形に曲げられるものです。また、型曲げに適した方法は、断面の形によって異なり、適応したさまざまな方法を用いる必要があります。
V曲げ加工方法
V曲げは基本の曲げ加工であり、多く使われる曲げ加工の方法です。
工程が1つの単純なものから、多工程に及ぶ複雑な曲げまで可能という特徴があります。そのため、金物の用途が広く、また汎用性が高いことが特徴で、実は日常的に目にすることが多いです。
V曲げができる材料の板厚は、0.3㎜の非常に薄いものから約30㎜程度までの厚みがあるものまで幅広いことも特徴です。技術や知識によって加工が可能な対象は異なり、設計によっても異なります。
エアベンディング
ワークが赤い3点だけの金物に触れるのがエアベンディングです。
ほかの面にワークが触れないために、曲げ加工に自在性があるという特徴があります。
3点に圧を加える方法であるため、折り曲げる角度が自由に設定できるというメリットを持ちます。また、パンチの位置の途中でも曲げ加工が可能です。
そのため、同じ型であっても、パンチの位置を変えるだけで、角度を変えられます。さらに、金物や型の種類や構造を変えることで断面のさまざまな施工が可能です。量産しないものや、試作における曲げ加工にも適用されます。
このことからも、自由度が高いことがわかるでしょう。
ただし、安定した精度を保つためには、高い技術が必要です。加えて、機械にも角度の精度が求められます。
曲げる部分の内半径が作りたい製品に適合しているか、フランジの長さが最小フランジを超えているかを確認することを忘れないようにしましょう。
ボトミング
ボトミングは、広く用いられる方法の1つです。
ボトミングという名称は、英語のボトムの意味から由来すると考えられています。
ワークがダイの面に触れることが、ボトミングの特徴です。加える圧が低くても精度が高い金物の曲げ加工を可能にできるボトミングは広く用いられています。ただし、施工後に、反発する場合があるため注意が必要です。
そのため、ボトミングでは反発が起きることを想定して計算を行います。反発を緻密に計算することで、仕上がりの精度が上がるのです。パンチの先端のV角度とダイのV溝の角度を完成より鋭くすることで、曲げを多くし精度を高めることが多いです。
ダイのV幅は、多様に変化するため、板厚とV幅を確認するようにしましょう。板厚のわずかな推移で精度が変わるため慎重な作業が必要です。
また、曲げる部分の内側の半径や、最小フランジの長さ、加える圧を考慮する必要があります。
コイニング
ワークにパンチとダイが密着する方法がコイニングです。加える圧が大きく、また必要な設備が大きくなってしまうため、最近ではあまり使われなくなっています。またコイニングでは金物が圧に耐える応用力が必要です。
コイニングは、繊細でありながら反発が小さいという特徴があります。spのため、精度の高い曲げ加工の仕上がりを実現できます。
ダイのV幅は、ボトミングより小さく、板厚の約5倍程度です。これはV幅の面積を小さくしてワークに圧を加えるためです。
一端を抑えてL字に曲げる方法
両端に圧を加える方法が、一端を押さえ、一端をパンチで曲げる方法です。押せ曲げは曲げ加工の原理を用いて、L字に曲げます。
一端のパッドの押さえる圧と、パットとダイに挟まれているウェッブの面積によって、仕上がりの精度が異なります。
ただし、緻密に反発を計算することができず、反発する力を計算して、曲げ込みを多めに作ることを得意としません。曲げ込みを多く作れず、余地がないため、反発が予想される直曲げが適さないことが多いです。
順に曲げていく方法
型に固定することなく、ラインの中で順に曲げ加工をする方法が送り曲げです。
ロールを3本使ったり、ロールを複数使ったりして、続けて曲げていくことも可能です。これらはそれぞれロール曲げやロール成型と呼ばれます。
ラインの中で順に曲げていくという特徴を活かすと、断面が複雑でも曲げ加工ができます。
製作したいものに合わせて、複雑さやロールを適用させられる方法です。
まとめ
今回は、金物の曲げ加工について紹介しました。
曲げ加工にはさまざまな種類があり、製作したい金物の種類や用途、断面の形などによって、曲げ加工が可能な方法が異なります。また反発の発生も違うため、適した加工方法を選ぶ必要があります。
金物の曲げ加工は、どこに依頼すれば良いのか迷う人が多くいます。そのようなときは板金の専門家に依頼すると良いでしょう。また、製作したい金物の曲げ加工が可能であるかも相談できます。
専門の知識と技術を用いて、適した曲げ加工で製品を作ってもらってみてはいかがでしょうか。
名古屋市の建築金物工事は三田工業株式会社に お任せください
会社名:三田工業株式会社
住所:〒452-0811
愛知県名古屋市西区砂原町185 メゾン余合103
TEL:052-502-4110 直通:090-3839-1078
営業時間:8:00~17:00
定休日:土曜日、日曜日